お知らせ & コラム NEWS / COLUMN
喉の不調と鍼灸 〜東洋医学の視点からみた対処法〜

季節の変わり目や乾燥する冬場になると、「喉の痛み」「イガイガ」「声のかすれ」など、喉の不調を訴える方が増えます。
風邪やインフルエンザ、花粉症などの原因もありますが、慢性的に喉の違和感がある方や、声を使う職業の方にとっては、喉の不調は日常生活に大きな支障をきたすこともあります。
こうした喉の症状に対して、東洋医学ではどのように捉え、鍼灸ではどのようにケアをしていくのか。今回はその観点から解説していきます。
喉の不調を東洋医学ではどう捉えるか
東洋医学では、喉の症状は単に「喉の炎症」だけではなく、体全体のバランスの乱れと深く関係していると考えます。特に以下のような臓腑や気の流れが注目されます。
・ 肺:肺は「宣発・粛降(せんぱつ・しゅくこう)」という作用があり、体表や喉・鼻などの粘膜を潤す役割があります。肺の気が弱まると、喉が乾いたり、声が出にくくなったりします。
・ 腎:東洋医学では腎が「精(せい)」を蔵し、成長・老化・生命力を司るとされますが、喉の奥、特に声帯周辺の機能とも関わりがあると考えられています。慢性的な声のかすれは腎の弱りと関連することも。
・ 肝:イライラやストレスで喉が詰まるような違和感がある場合、肝の気の滞り=「肝鬱気滞(かんうつきたい)」が原因とされることがあります。「梅核気(ばいかくき)」と呼ばれる、喉に何か詰まっているような症状も、肝気の乱れとされます。
・ 胃熱・咽痛:暴飲暴食や辛い物・脂っこい物の摂り過ぎなどで「胃熱」が生じると、炎症性の咽頭痛が起きやすくなります。
つまり喉の症状は、局所だけではなく「肺」「腎」「肝」「胃」など、様々な臓腑や気血水のバランスと深く関係していると考えられているのです。

鍼灸治療ではどうアプローチするか
鍼灸治療では、まずはその人の体質や症状の背景を丁寧に見極めます。そのうえで、以下のような方法でアプローチしていきます。
1. 局所のツボへの施術
喉の周囲には、直接喉の症状に関係するツボが多数あります。
・ 天突(てんとつ):胸骨のくぼみにあり、喉の詰まりや咳に用いられる。
・ 廉泉(れんせん):喉仏の下に位置し、発声や咽頭の不調に有効。
・ 扶突(ふとつ)・人迎(じんげい):首の側面にあるツボで、喉の痛みや腫れに対応します。
これらのツボに鍼やお灸を施すことで、局所の血流を改善し、炎症や違和感を和らげます。
2. 全身のバランスを整えるツボ
喉の不調は「体の声」とも言えるため、全身の調整も大切です。
・ 太淵(たいえん)・列缺(れっけつ):肺の経絡上にあり、呼吸器系の調整に効果的。
・ 太谿(たいけい)・腎兪(じんゆ):腎を補い、慢性的な喉の症状や声の衰えに。
・ 内関(ないかん)・肝兪(かんゆ):ストレス性の喉の詰まりやイライラに効果が期待されます。
また、喉の不調が長引いている方には、体全体の「気の巡り」「血の巡り」を整えるよう、全身調整の施術が組み込まれることも多いです。
3. お灸による温熱刺激
慢性的な喉の乾燥やかすれには、お灸による温熱刺激が有効な場合があります。とくに寒い季節は、体を内側から温めることが症状の軽減につながります。
鍼灸のメリットと注意点
鍼灸は薬に頼らず、身体本来の治癒力を高めていく方法です。副作用が少なく、慢性的な不調の改善に適しています。
また、喉の症状だけでなく、全体の体調管理にも効果があり、定期的にメンテナンスされる方も多くいらっしゃいます。
ただし、急性の感染症(インフルエンザ、咽頭炎、扁桃炎など)や発熱がある場合は、まずは医療機関での診断・治療が優先です。鍼灸はあくまで、体質改善や慢性的な症状のケアに向いていることを理解しておくことが大切です。
まとめ
喉の不調は、単なる「のど風邪」だけでなく、東洋医学では全身のバランスの乱れとしてとらえられます。
肺や腎、肝などの臓腑の状態、気血の流れを整えることで、喉の違和感が改善することも多くあります。
慢性的な喉の症状にお悩みの方は、ぜひ一度、東洋医学の視点を取り入れた鍼灸治療を試してみてはいかがでしょうか。
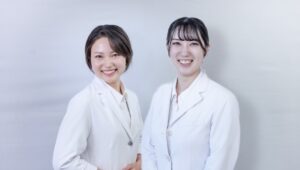
ご予約はこちらから
\相談だけでも大丈夫ですのでお気軽に/
はじめての方も安心の返金保証制度をご用意しております。
たった一度のご来院でも、我々の専門知識と確かな技術で
お客様のお悩みの症状に対する概念を、きっと変えられると思ってます。
是非一度お気軽にご相談ください。






